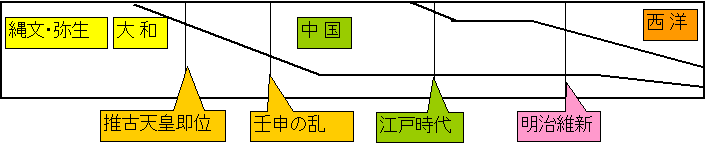| 推古天皇即位 |
日本に仏教文化が伝来し、一気に中国文化が花開いたのは、飛鳥時代である。聖徳太子が蘇我馬子と権力を握り、遣隋使・遣唐使を派遣する。
大量の文化と外交人が渡来し、圧倒的な影響を受けた。
仏教文化が、古代の日本文化と融合し、独自の文化として根づくには、平安時代をまたねばならない。
江戸時代の町人文化を見るとき、平安時代の「かな文化」、和歌の下敷き無しでは語れないと思う。
文化の融合の点では、現代日本も欧米文化一辺倒ではなく、日本文化が融合した形で、21世紀に新たな文化の創造があるかもしれない。 |
| 壬申の乱 |
大海人皇子が兄の天智天皇側を破った国内指折りの内乱である。
勝った天武天皇が強大な権力を集め、推古天皇に始まった天皇制が制度として確立するに至った事件である。
私が大津に住んでいた頃、よく瀬田川沿いを散歩した。この川に架っているのが日本三大名橋「瀬田の唐橋」である。天智天皇が没した翌年、西暦672年7月22日、天智天皇の子「大友皇子」は、ここ瀬田の唐橋で大海人軍の総攻撃に敗れた。 |
| 江戸時代 |
戦国時代、キリスト教の伝来に象徴される南蛮文化が日本に押し寄せる。
家康が天下を統一し、孫の家光時代に鎖国政策がとられることにより、外国文化の流入が極端に少なくなり、250年にわたる日本独自の文化が醸成される。
私にとっては、この芳醇な文化が好ましく、江戸時代に惹かれるのである。 |
| おわりに |
明治維新後の欧米文化の流入、太平洋戦争敗北後のアメリカ文化お仕着せには触れないことにする。
文化の重層の上に形成されている現代日本人。表面的には新しい文化ほど、大きく影響を与えているように見えるが、古い文化ほど深く・強く人間形成の根幹にかかわっているように思える。
私は「縄文人」の末裔に違いないと思うのだが、先祖は地球が温暖であった縄文時代、東北日本の地で暮らしていた。ブナの自然林を背後に持ち、川沿いに開けた地で、「木の実」のなる木を育て、山の幸・海の幸(食物だけでない)に囲まれてゆったりと暮らしていた。 |