| マニアックな江戸時代史 |
| マニアックな江戸時代史 |
| 私の興味は、「江戸時代の人物史」歴史上の人物と同じ空気を吸い、会話するのはとても楽しい |
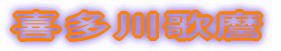 |
六大浮世絵師・三大美人絵師、「歌麿」イメージは、 ある挿絵を見てから大きく変わった。 |
| 1.はじめに 2.「画本虫撰」 3.歌麿の半生
・十代の歌麿 ・浮世絵師「北川豊章」 ・歌麿デビュー ・狂歌絵本に集中 ・歌麿絶頂期 ・写楽登場 ・重三郎の死 ・晩年 |
|
| はじめに | |
| 世界的名声に輝く美人画の最高峰であり、美人大首絵という新趣向を生み出し、傑作の数々は「神聖な美」 とも称えられている。又、芸術的な技術については、単純化された色面構成と線描のリズムによって、 女性の官能美の典型がつくり出されており、その生活や心理の描写にも新しい工夫がみられる。 これが、一般的な「歌麿」の評価であり、紹介のされ方である。 しかし、苦悩に満ちた歌麿の人生や作品についての記述は少ない。 |
|
| 狂歌集「画本虫撰」の挿絵 | |
| 細密画と言っていい写実的なタッチ、大和絵を連想させる構図、この 作品を初めて見たとき、私はショックを受けると共に、今まで漠然と 抱いていた「歌麿のイメージ」が崩れ去った。 私は、自分がそれまでに目にしてきた「美人画」と、この挿絵との 線を結ぶために調べてみた。 以下、歌麿の半生を推論もまじえながら記述してみる。 「画本虫撰」:宿屋飯盛(石川雅望)が編集した狂歌集 |
|
| 歌麿の半生 | |
江戸町人文化隆盛の中、 充実した時を過ごした 十代の歌麿 |
歌麿の出生は、今もって不明である。 狩野派の末端の絵師「鳥山石燕」門下で、同門の春町、燕十、長喜 らと共に過ごし、師が俳句仲間として親しかった当時の浮世絵界の 大御所北尾重政にも可愛がられた。 十代は、意識することなく、日々の暮らしの中で江戸町人文化の 空気を胸一杯に吸い込んでいた。 周囲からは、絵の才能も認められ充実した時を過ごした。 明和2年、歌麿12歳の時、春信が錦絵を創始し、浮世絵も 隆盛の緒を切っていた。 |
| ほろ苦いデビューと 屈辱の時代 浮世絵師 「北川豊章」 |
安永4年11月(23歳)、富本浄瑠璃の正本の表紙でデビュー。 落款は、本名と師から一字もらい「北川豊章」である。 この時期、江戸は黄表紙出版前期にあたる。地本問屋の老舗、 西村与八(永寿堂)は、新進の黄表紙の挿絵作家を求めていた。 歌麿も期待された一人であったが、一つ年上の「鳥居清長」に敗れる。 これ以後の安永年間は、師である石燕の伝手で細々と作品を 発表するという屈辱の時を過ごす。 一方、清長は春信・磯田湖竜斎と続く「美人画」の後継者として 飛躍していく。 |
29歳、蔦屋から 歌麿デビュー |
年号が天明に変わり、江戸の出版界は、若手の台頭が著しい。 特に、蔦屋重三郎は、鱗形屋の後を引き継ぎ、喜三二・重政コンビで 黄表紙出版の成功をおさめた。 才能を持つ若手への投資を積極的に行い、その独創的な企画力で、 地本問屋のトップに踊り出ようと野心に燃えていた。 天明元年、同門の志水燕十とのコンビで「身貌大通神略起」を 蔦屋から出版。 この作品ではじめて「歌麿」を名乗る。29歳の時だった。 |
| 自信を深め、独自の画境を 切り開く夜明け前である。 狂歌絵本の 挿絵に集中 |
天明2年秋、蔦重は忍岡(現上野)の料亭に、四方赤良・朱楽菅江 ・恋川春町・朋誠堂喜三二・市場通笑・芝全交・岸田杜芳・森羅万象 ・南陀伽紫蘭・・・の戯作者・狂歌師、北尾重政・勝川春章・鳥居清長等 の浮世絵師を集め、催主「歌麿」のお披露目を企画した。 この時期の一流人が一堂に会した場は、まだ実績に乏しい歌麿に とって晴れがましいと同時に不安な気持ちで一杯だったに違いない。 天明3年、吉原から日本橋に進出した若干34歳の蔦重は、 勢いに乗っていた。 この頃、江戸で一躍ブームになった狂歌に乗り、蔦重は狂歌絵本の 出版を企画し、絵師に「歌麿」を起用した。 歌麿は、蔦重の期待に応え、狂歌絵本に集中した。天明6年から 寛政2年にかけ13種の絵本に170図の挿絵を描いた。 その中の、一作品が「画本虫撰」である。 また、有名な秘画(春画)「歌まくら」もこの時期に描かれている。 しかし、「美人画」で絶頂を極めている清長は、 まだまだ遠い存在であった。 |
| 歌麿ブレーク、 一躍浮世絵界の寵児に 歌麿、絶頂期 |
狂歌絵本で成功した蔦重は、浮世絵の二枚看板の一つ美人画の 制覇を目指す。蔦重と歌麿は、清長らの全身群像図が主流だった 美人画に「大首絵」という企画を持ち込んだ。その新鮮さがうけ、 人気を勝ち取っていく。 寛政4年から6年にかけて、歌麿絶頂期を迎える。私達が目にする 作品の大多数がこの時期に制作されている。 市井のアイドルたちを描いた「当時三美人」等、妓楼の美女 「まき絹・花扇・・・」、女性の内面まで写し取っていると評価の高い 「婦人相学十躰」「婦人人相十品」「歌撰恋之部」等。 これより前、寛政3年3月、山東京伝の洒落本3冊が町触れに 違反したことにより、京伝は手鎖50日、蔦重は財産半分没収の 処分にあった。蔦重は、この災禍をばねにし、歌麿と美人画の制覇に 邁進した。ここに来て、歌麿は「清長」に追いつき、追い越した。 ←歌撰恋之部 物思恋(モデルは朝日屋後家か?) |
蔦重と袂を分かつ 写楽登場 |
清長が退いた後、西村屋与八は巻き返しの機会を狙っていた。 そして、当時若干23歳だった新進気鋭の「歌川豊国」の争奪戦に 勝ち残り、「役者舞台の姿絵 紀伊国屋」で豊国の名声は うなぎのぼりとなる。 蔦重は、これに対抗すべく「役者絵」に乗り出し、「写楽」を発掘する。 写楽に傾倒していく蔦重と歌麿は袂を分かつ。絶頂期にあった 42歳の歌麿は自信に満ちていた。蔦重にあてつけるかのごとく作品を 発表していく。「北国五色墨」は、今まで誰もが題材することはなかった 遊郭吉原の最下層の女性達に肉薄した迫力ある作品である。 一方、蔦重は寛政6年5月、写楽の売り出に成功するが、 二期三期四期と進むにつれ凋落の一途をたどり、 翌年には「役者絵」から撤退することになる。 寛政7年、歌麿と復縁し、名作「青楼十二時」を発表する。 ←「北国五色墨」 |
| 寛政の改革に立ち向かい、 事業に失敗した疲れが 一気に押し寄せ 重三郎、死す |
蔦屋重三郎は、寛政3年の財産没収後、無理を重ね役者絵の失敗が 大きく響き、寛政8年には病に伏し、翌9年5月6日47歳で永眠する。 一方、歌麿の名声は衰えず版元からの製作依頼が相次ぎ、 その地位を守るためか、多作の時期が続く。当然、作品の質も落ち、 全盛期の面影もなくなる。 気が付けば、師石燕の死に始まり、先輩戯作者達も次々引退し、 真に語るべき友も亡くなっていた。自分を育ててくれた重三郎の死は ボディブローのように効いてきたに違いない。 名声の衰えに対する恐れと寂しさを紛らわすための 多作だったに違いない |
晩年 |
文化元年5月、「太閤洛東五妻遊観之図」が家斉の大奥生活を批判 したとして、入牢の憂き目にあい、手鎖50日の処分を受ける。 これを機に、気力も衰え、文化3年54歳で没す。 |
| おわりに | |
| 「歌麿」を最初に取り上げたのは、なぜなのか自分でも定かでない。おそらく、自分にとって数多い 浮世絵師の中で最も人物像がクリアだったせいだと思う。 それゆえに、私個人の偏見に満ちた記事になったかもしれない。 浮世絵については、描きたいことが沢山ある。間を置いて、また書きたいと考えている。 |
|
| 沢山の文献を参考にさせていただきました。お礼申し上げます。 | |